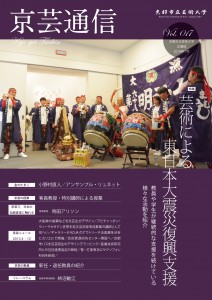京芸通信vol.17を発行
卒業生インタビューの更新(アーティスト 松井智惠さん)
京都芸大を卒業し,多方面で活躍する先輩方を全4回にわたってお送りする「卒業生インタビュー」を更新しました!
3月はアーティストの松井智惠さんです。
3回目の今回は「作品とは何か,芸術とは何か」をテーマに語っていただきました。
ぜひ御覧ください。
ギャラリー&コンサートガイド2014春夏号の刊行
この度,「ギャラリー&コンサートガイド2014春夏号」を刊行しました。
本紙は,2014年4月から9月まで開催するイベントを多数掲載しております。中でも,開館5周年を迎えるギャラリー・アクアにおける記念展や,本学芸術資料館が収蔵する貴重な資料を展示する収蔵品展,サクソフォン科目を新設し,本格的な吹奏楽のコンサートに挑む音楽学部の学生のコンサート,初めて受講する方にも分かりやすいと好評の日本伝統音楽研究センターの講座など,京都芸大の教育研究の成果を体験・実感いただけるイベントを御案内したリーフレットとなっております。
以下及びイベントページに掲載している他,本学窓口,ギャラリー@KCUA,京都市役所,地下鉄各駅等で配布しております。
本紙を御覧いただき,是非,御来場下さい。
【京芸友の会】寄付金の実績と使途の報告
この度,京芸友の会制度により御寄付をいただいた寄付金の実績と使途について,報告いたします。
なお,いただいた寄付金を活用させていただき,学生選書ツアーを実施して,図書館に新たに本を購入しました。
その様子のレポートも掲載していますので,併せてご覧ください。
寄付者の皆様には,改めて深く感謝申し上げます。
平成25年度学部卒業式並びに大学院学位記授与式を開催
平成26年3月24日,平成25年度美術学部・音楽学部卒業式並びに大学院美術研究科・音楽研究科学位記授与式を執り行いました。
美術学部136名,音楽学部59名,美術研究科修士課程61名,音楽研究科修士課程18名,美術研究科博士課程3名,音楽研究科博士課程2名が,門川大作京都市長をはじめ来賓の皆様,保護者の皆様,教職員に温かく見守られ,卒業式並びに学位記授与式に参加しました。
今年も,例年どおり,美術学部・大学院の多くの学生は,交通局,京都水族館との連携事業から生まれたキャラクターのオオさん,ショウさん,建畠学長,人気のキャラクター,動物など,自作のユニークな衣装で参加し,また,音楽学部・大学院の卒業生からは,美しい歌声が披露されるなど,芸術大学らしい演出がなされ,会場を笑顔で包みこみ,和やかでアットホームな式となりました。
卒業生・修了生の皆さん,本当におめでとうございます。
本学一同,皆さんのご活躍を心から期待しております。
<学長式辞>
本日,ここに,門川大作京都市長をはじめとして,美術教育後援会,音楽教育後援会,美術学部同窓会,音楽学部同窓会の御来賓の皆様の御列席のもとに,美術学部卒業生136名,音楽学部卒業生59名,美術研究科修士課程修了生61名,音楽研究科修士課程修了生18名,美術研究科博士課程修了生3名,音楽研究科博士課程修了生2名の卒業式ならびに修了式を挙行するにあたりまして,式辞を述べさせていただきます。
学部卒業生,大学院修了生のみなさん,おめでとうございます。これから皆さんは社会へと巣立ち,あるいは大学院でさらに勉学を深めることになりますが,いかなる方向に進まれるにせよ,本学の恵まれた環境のもとで,また京都という素晴らしい都市の文化の伝統に触れながら学んだ歳月は,皆さんの人生にとってきわめて大きな意味をもつことになるでしょう。
周知のように本学は芸術系大学としては日本では最も長い歴史を有しています。百三十有余年の間に近代芸術の屋台骨を支えるというべきオーソドックスな人材を数多く輩出すると同時に,また芸術の既成概念を一気に更新するような独創性を発揮する才能をも世に送り出してきたのです。アカデミズムと在野精神,正系と異端,文化の伝承と革新という本来なら相反するはずの要素が共存しているところが本学の特質なのですが,考えてみれば,それは京都というまちそのものの魅力でもあるに違いありません
京都とは不思議なまちであって,日本を代表する古都としてあまねく世界に知られているにもかかわらず,前衛的な気風にあふれてもいます。こうした二面性は実のところ,一枚の紙の両面のように不可分な関係にあるというべきかもしれません。伝統的な文化資源の厚みが,そのまま斬新な創造活動に基盤をなしているというところが,京都というまちの凄さであり,アートに関わる者を魅してやまない求心力をなしてきたのです。
それにしても,私たちはなぜ表現において新しくなければならないのでしょうか。このまちにこれほど素晴らしい文化資源があるならば,それを遵守するだけで十分ではないか。歴史上の偉大なる遺産を乗り越えることなどできるわけがない。私たちはただ古典を忠実に学んでいればいいのだ・・・・。日々新しくあれという主張に対しては,そうした反論が聞こえてきそうです。
しかし私たちが古典を学ぶのは,必ずしも古典そのものと同じような作品を作り出すためではありません。あえて逆説的な言い方をするなら,私たちはむしろ古典との違いを生み出すためにこそ,小難しい哲学用語を使わせていただくなら古典からの差異(ディフェランス)を超出させるためにこそ,古典を学ばなければならないのです。
私たちは古典を生み出したアーティストたちとは別の時代を生きています。社会的な状況もアートを取り巻く環境もまったく異なっているはずの今という時代に,古典と同じ発想と方法で制作するならば,それは単に伝統を墨守するだけの内的な必然性を欠いた形式的な悪しきアカデミズムに陥ってしまうでしょう。
とすると今度はこんな反論が出てくるかもしれません。新しくありさえすればいいのなら,何も古典など学ぶ必要はないのではないか。しかし新しさとは,何かに対する新しさであって,何もないところからは新しさが出て来るべくもないのです。私たちにとっての輝かしい古典であるロマン主義も印象派も,歴史に深く学んだ音楽家や美術家による“過去からの差異”として生み出されたのです。まったくもってピカソの独創であるキュビスムも,セザンヌに向けられた新たな眼差しやアフリカの部族芸術から受けたインスピレーションがなければ誕生することはなかったでしょう。
ダダイズムは一切の歴史を拒絶したではないか。すべてに対するタブララサ(白紙還元)を敢行し,反芸術を唱えたではないか。そういう意見も出てきそうです。しかし反芸術とはあくまでも芸術との対概念として成立するものであり,自明の理として,芸術がなければ反芸術もありえないのです。反芸術がある限り,芸術は消滅しないというアイロニーは,かえってマルセル・デュシャンらのダダの運動の栄光を告げているとさえいえるかもしれません。
アーティストならざる鑑賞者や研究者にとっても,同じことは言えるはずです。オーディエンスや読者として古典を聴き,また見る,読むということは,今という時代の感性によって古典を再発見する,そこに新たな意味を見い出すということでもあります。そうである限り,古典には最終的,究極的な解釈はありえず,時代と共に常に再解釈され,新たな意味をもって蘇ってくるのです。言い換えるなら,どのような時代の眼差しにも応えうる永遠の生命をもつ作品だけが,古典と呼ばれる資格があることになるでしょう。たとえば源氏物語は,かつては与謝野晶子や谷崎潤一郎が現代語訳を手掛け,戦後は円地文子や田辺聖子が,最近では瀬戸内寂聴がと,数多くのすぐれた文学者たちが翻訳=新解釈に取り組んできましたが,そのどれがベストというわけではなく,それぞれにその時代ならではの真実をはらんでいたというべきでしょう。
これから社会に向かって羽ばたこうと新たな意欲に燃えている皆さんに,少々,古めかしくもある古典の話ばかりをしてしまったようです。今まで述べてきたことは要するに温故知新ということに尽きると私は思っています。古きをたずねて新しきを知るというこの論語の言葉は,新たなるアートの創造を志す者にとっての永遠の真実であるに違いありません。
これから皆さんが出て行かれる世界ではさまざまな難問が待ち構えていることでしょうが,若々しいエネルギーに満ちた皆さんの活躍によって,必ずや新たな展望が切り開らかれるものと期待しています。本学での勉学を基盤にしながら,また時には改めて古典を顧みながら,アートの王道をたくましく歩んでください。
皆さん,本当におめでとうございます。これをもってお祝いの言葉とさせていただきます。
平成26年3月24日
京都市立芸術大学長
建畠晢
卒業生インタビューの更新(アーティスト 松井智惠さん)
京都芸大を卒業し,多方面で活躍する先輩方を全4回にわたってお送りする「卒業生インタビュー」を更新しました!
3月はアーティストの松井智惠さんです。
最終回は「答えを求めて」をテーマに語っていただきました。
ぜひ御覧ください。
平成26年度(2014年度) 京都市立芸術大学入学試験 追加合格について
平成26年度(2014年度)美術学部及び音楽学部入学試験について,追加合格は行いませんのでお知らせします。
【受賞情報】修了生の宮本佳美さんが,平成26年度五島記念文化賞美術新人賞を受賞
美術研究科修士課程絵画専攻(油画)の修了生である宮本佳美さんが,平成26年度(第25回)五島記念文化賞美術新人賞を受賞されました。
この賞は,公益財団法人五島記念文化財団が,「芸術文化の分野での有能な新人及び地域において創造的で優れた芸術活動を行っている方々の顕彰・助成を行い、日本文化の向上・発展に寄与すること」を目的に実施されているものです。
詳しくは,公益財団法人五島記念文化財団のホームページをご覧ください。
関連ページ
平成26年度京都市立芸術大学入学式を開催
平成26年4月10日,平成26年度京都市立芸術大学入学式を執り行いました。
美術学部135名,音楽学部65名,美術研究科修士課程62名,音楽研究科修士課程19名,美術研究科博士後期課程12名の総計293名が,門川大作京都市長をはじめ来賓の皆様,保護者の皆様,教職員に温かく見守られ,入学式に参加しました。
丸池の桜が新入生の皆様をお迎えし,初々しい新入生の皆様の大きな期待に満ちた表情が輝く,清々しい入学式となりました。
また,入学式後には,多くのクラブが新入生を勧誘し,能楽部では,能管の演奏を披露しました。
新入生の皆さん,御入学おめでとうございます。
皆様の大学生活が,実りある人生の1ページとなりますように。
本学一同,心よりお祝い申し上げます。
<学長式辞>
本日ここに,門川大作京都市長をはじめとして,経営審議会,美術教育後援会,音楽教育後援会,美術学部同窓会,音楽学部同窓会のご来賓の皆様のご臨席を仰ぎ,美術学部135名,音楽学部65名,美術研究科修士課程62名,音楽研究科修士課程19名,美術研究科博士課程12名,総計293名を迎える入学式を挙行するに当たり,京都市立芸術大学を代表して,心からのお祝いの言葉を申し述べさせていただきます。
皆さんが晴れて入学を果たした本学は,開学以来134年という芸術系大学としては我が国で最も長い歴史を誇っており,文字通り日本の近現代芸術の屋台骨を支える美術家たちを輩出してきました。62年前に創設された音楽学部も国際的に注目されている数々の輝かしい才能を世に送り出すようになっています。皆さんも,そのような燦然たる芸術の歴史に自らも身を投じるのだという意欲とプライドをもって本学に入ってこられたことでしょう。私たちは皆さんの若々しい情熱を頼もしく思い,夢の実現のために一緒に歩んで行こうと考えています。
本学の優れた教授陣やスタッフによる充実した少人数教育は,芸術の道を志す者にとっての理想的な環境であり,そこでの勉学や研究は必ずや皆さんの成長に大きく寄与することでしょう。皆さんに与えられたもう一つの特権。それは,まさに本学が京都という町に位置しているという点にあります。言うまでもなく京都は世界有数の卓越した文化財と重厚な伝統で知られる都市ですが,単に過去の遺産だけに安住するのではなく,新たな文化,独創的な芸術の発信基地としての活気にも満ちています。この素晴らしい町の伝統と革新の息吹に触れながら学生生活を過ごせるということ。それは皆さんにとって他にかけがえのない経験になるでしょう。
京都の市民に支えられた本学は,この町の文化的シンボルとしての役割を担ってもいます。学生諸君もまた,暖かい目で見守ってくれる市民の方々の期待を背に勉学にいそしんで下さい。すでにご存じかもしれませんが,本学は京都駅の東側の地区に移転するという計画を進めており,実現には十年ほど時間を要するにしても,将来に向けて京都市のシンボルとしての性格は一層,強化されていくことになるでしょう。
さて皆さんは,アーティストを目指して,あるいはアートの研究者や教育者を目指して,本学の門をくぐってこられたに違いありませんが,アートへの道を志すとは,しかし実際にはどういうことなのでしょうか。鑑賞者としてではなく,また趣味としてでもない,いうならば職業としてのアートへの道をいま皆さんは歩み出そうとしているのです。それは他のいかなる仕事にも増して魅力的な道,挑戦に値する素晴らしい道ですが,またさまざまな困難に満ち,時には挫折を強いられることもあるであろう,極めて厳しい道でもあります。アーティストを目指すことは決して平坦な道,平穏無事な道ではないのです。
ここで私はアートへの道を志すことの素晴らしさ,厳しさとを,またアーティストであることの使命を改めて考えていただくための参考として,皆さんの大先輩である一人の女性画家のことをお話しすることにしましょう。
草間彌生さんは1929年に生まれ,本学の前身である学校の日本画科に学ばれました。草間彌生さんというと,皆さんは特異な精神的病理を抱えたアウトサイダーである,美術のいかなる規範とも無縁であるゆえの天才であると思っておられることでしょう。たしかにアウトサイダー的な側面は草間さんならではの魅力をなしているに違いありません。彼女自身,他のアーティストから影響を受けたことは一切ないと公言もしています。
しかし興味深いのは,彼女は京都に学んだ時期に村上華岳と速水御舟を意識していたとも述べていることです。華岳は本学出身ということもあって,作品を見る機会があったのでしょうが,宗教画にも通じるスピリチュアルな(霊的な)ところのある画風に,草間さんは常にアナザーワールド(異界)を描こうとする自らのイメージと呼応するものを感じたのかもしれません。速水御舟もまた京都と縁の深い画家ですが,草間さんは御舟はマボロシを見る画家であり,その意味で私のライバルだとも述べています。御舟の柘榴などを描いた静物画は,徹底した細密描写が,草間さんのいうマボロシに通じるまでの一種不穏なリアリティーを生み出しており,草間さんはそれに対抗するかのように,京都時代に日本画の技法で玉葱などの細密描写を試みてもいるのです。
天才は天才を知るといえばそれまでの話ですが,脇目も振らずわが道を驀進してきた草間さんが,画家としての自己形成期に,自らのライバルと見なしうる存在を先達の中に認めていたという事実は注目に値するでしょう。
1950年代の終わりにニューヨークに移住してからの草間さんは,網目と水玉が連鎖する絵画の大作などによって,水玉の女王と称されるようになりました。同じパターンの無限の反復は,彼女の特異なオブセッション,強迫観念によるもので,まさに他のいかなるものの影響も受けていない,純粋に内的な衝動に突き動かされた制作というべきでしょう。
今日にいたるまで常同反復という方法は一貫して維持されていますが,ではなぜそのような,考えようによっては自分だけの世界に閉じこもっているともいえる彼女のオブセッシブな作品が,今日では現代美術のファンの層を越えた多くの人たちを,さまざまな国,さまざまな年齢の人たちを魅了するようになったのでしょうか。
オブセッションとは時には不気味なものであり,トラウマに満ち,また精神的な抑圧を背景にしたものでもあります。それはたしかに自己の内面に個人的に抱えこんでしまった厄介なものなのですが,しかし,あえて逆説を持ち出すなら,むしろそうであるがゆえにこそ自己と他者とが心を通じ合うコミュニケーションの基盤ともなりうるのではないでしょうか。悩みを抱えた人たちにかえって私たちは心を開き,優しい気持ちをもって接することができるというのは,むしろ普遍的な心の働きなのではないでしょうか。
草間さんの強烈といえば強烈なオブセッションの世界は,そうであるがゆえにこそより開かれた,より豊かな相互的なコミュニケーションを可能にしている。そう私は考えているのです。私たちもまた日常生活の中で,それぞれのトラウマや悩みを抱えながら生きています。草間さんの作品に触れることで,その世界と心を開いて対話することで,私たちもまた深いところで心の救済を覚えるのではないか。作品がもたらす豊かなコミュニケーションによって,自分と世界との同時的な救済をはかる。そのことこそが,草間さんを私たちの時代の真に偉大なアーティストにしているというべきでしょう。彼女が「私大好き」という大いなるナルシストであることと,ラブ・フォーエヴァー(愛はとこしえ)という平和と大いなる愛の思想の持ち主であることとは,まさに一つに結び付いているのです。
皆さんは学部で,また大学院で,この大学が誇る教授陣に学び,また草間さんをはじめとする敬愛に値する先輩たちの仕事にも啓発されながら,美術家としての,音楽家としての,また研究者としての自らの世界を築き上げていくことになるでしょう。どうか京都市立芸術大学の恵まれた環境を存分に生かして,これからの皆さんにとってのかけがえのない特権的な日々である大学生活を充実したものにしてください。本日は保護者の方々も大勢お見えでいらっしゃいますが,学生たちの成長を暖かい目で支えてくださるようお願い申し上げます。本日は本当におめでとうございます。
これをもってお祝いの言葉とさせていただきます。
2014年4月10日
京都市立芸術大学長
建畠晢
【受賞情報】渡邉さちさんが,第24回ホビー大賞グランプリを受賞
 美術学部染織専攻4回生の渡邉さちさんが,作品「姉へ」で,第24回ホビー大賞グランプリを受賞されました。
美術学部染織専攻4回生の渡邉さちさんが,作品「姉へ」で,第24回ホビー大賞グランプリを受賞されました。
この賞は,一般社団法人日本ホビー協会が主催するもので,「人々や社会に感動,豊かさ,楽しみ,温もりなどをもたらす創造性,デザイン性に富んだ創作活動または作品」に贈られる賞です。
本作品は,渡邉さんのお姉さんの御結婚に際し,渡邉さんからプレゼントされたもので,お姉さんの小学校の時の作文や友人からの手紙を,シルクスクリーン技法で布にプリントし,ビーズ刺繍とともに縫い合わせて作られました。
本作品をはじめ,受賞作品は,平成26年4月24日(木曜日)から26日(土曜日)まで,東京ビッグサイト東京国際展示場にて展示される予定です。
詳しくは,一般社団法人日本ホビー協会のホームページをご覧ください。
【京芸友の会】ご寄付をいただいた皆様のお名前,応援メッセージのページを更新
この度,京芸友の会制度により御寄付をいただいた皆様のお名前と応援メッセージのページを更新しました。
改めて,寄付者の皆様に深く感謝申し上げますとともに,いただいた御寄付については,皆様の御意志に沿って,有効に活用させていただきたいと存じます。
詳細は,京芸友の会のページをご覧ください。
声楽専攻教員募集のお知らせ
京都市立芸術大学では,声楽専攻の教員を募集します。
募集の詳細については,「教員の公募について」をご覧ください。
採用予定日:平成27年4月1日
応募書類提出期限:平成26年7月15日※必着
教務学生課音楽教務担当
ARTIST WORKSHOP @KCUA 参加者募集のお知らせ
 京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA(アクア)では,昨年度にアピチャッポン・ウィーラセタクン氏と山出淳也氏を講師として招聘したアーティストの為のワークショップ第二弾を開催いたします。
京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA(アクア)では,昨年度にアピチャッポン・ウィーラセタクン氏と山出淳也氏を講師として招聘したアーティストの為のワークショップ第二弾を開催いたします。
今年度は計3回,1. 絵画,2.写真,3.インスタレーションの3つのジャンルのワークショップ事業を実施します。
第1回目となる絵画のワークショップでは,ニューヨークからエレン・アルトフェスト氏を講師として招聘します。
アルトフェスト氏は,昨年のベニスビエンナーレにも出展,New Museum(ニューヨーク)やWHITE CUBE(ロンドン)で個展を開催するなど,海外で注目の高まっているアーティストです。
今回ワークショップの為にアルトフェスト氏が考えた講義内容や制作課題は,とても充実した内容になっており,新しい技術の習得だけではなく,作品制作のステップアップへ繋がるようなワークショップになることが期待できます。
ただいま,このワークショップへの参加者を募集中です。
ペインターの皆様,是非ご参加くださいますようお願い致します。
詳細はWEBを参照ください。
【WEB(WEBサイトからご応募できます)】
http://gallery-akcua.org/ARTIST-WORKSHOP/THE-HUNDRED-STEPS/index.html
【募集内容】※申請者は,下記日程の面接に参加できることを条件といたします。
| 締切 | 2014年5月26日(月曜日) |
| 面接 | 5月30日(金曜日)17:00 ~ (書類審査を通過した方のみ) |
| 審査結果通知 | 5月31日(土曜日) |
| 募集人数 | 6~8名程度(グループ不可) |
| 応募資格 | ・英語での簡単なコミュニーケーションスキルを有すること ・絵画作品の制作歴があること ・35歳以下の若手作家であること ・下記のスケジュールでワークショップに全日参加できること ※その他の条件については,WEBサイトの注意事項を参照ください。 |
【受賞情報】ビジュアル・デザイン専攻の学生及び非常勤講師が日本タイポグラフィ年鑑2014受賞
「NPO法人日本タイポグラフィ協会」が主催する「日本タイポグラフィ年鑑2014」で,美術学部ビジュアル・デザイン専攻の学生及び非常勤講師の作品が下記のとおり受賞し,年鑑に掲載されました。タイポグラフィ年鑑への掲載はコンペ形式により決まります。
学生部門
入選 大橋 千晶さん(2013年度 4回生)
時藤 愛さん(2013年度 4回生)
小林 まり絵さん(2013年度 4回生)
田中 紀さん(2013年度 4回生)
橋本 隆史さん(2013年度 4回生)
楠 麻耶さん(2013年度 修士2回生)
ロゴタイプ・シンボルマーク部門
部門賞 藤脇 慎吾 非常勤講師
その他,同専攻卒業生が多数入選されています。
皆様,おめでとうございます。
詳しくは,日本タイポグラフィ協会のホームページをご覧ください。
関連ページ
京都芸大サマーアートスクール2014開催のご案内
この度,京都市立芸術大学美術学部では,市立芸大ならではの芸術教育の知識や技術を生かして,多くの皆様に,芸術文化に触れ,学ぶ機会を提供するため,サマーアートスクール2014を開催しますので,受講者を下記のとおり募集します。
9回目となる今回は,現在設置されている美術学部の各専攻から,実技・講義とも多彩な内容の8講座を予定しています。本学の教員や非常勤講師などが直接指導します。
また,本講座は,教員免許更新制に対応した「平成26年度教員免許状更新講習」(教科指導,生徒指導,その他教育の充実に関する講座(計18時間))内の専門分野実習(12時間分)の対象講座としても実施します。
多くの皆様のご参加をお待ちしております。
◆詳細はこちらをご覧ください
| 1 開催期間 | 平成26年8月5日(火)~8月10日(日) ※教員免許状更新講習受講の場合は8月4日(月)〜11日(月) |
| 2 場 所 | ・京都市立芸術大学 (京都市西京区大枝沓掛町13-6) ・堀川御池ギャラリー(京都市中京区油小路通御池押油小路町238-1) |
| 3 講座内容・定員等 | サマーアートスクール案内ホームページをご参照ください。 ※各講座の開催日時は講座毎に異なります。 |
| 4 申込期間 | 平成26年6月2日(月)~6月27日(金)(必着) |
【受賞情報】本学在学生,卒業生,修了生がコンクール等で受賞
本学の在学生,卒業生,修了生が各地で行われたコンクール等で受賞しました。
結果は,以下のとおりです。
美術関係
第24回ホビー大賞
グランプリ
渡邉 さちさん (美術学部 染織専攻 4回生)
アートアワードトーキョー丸の内2014
グランプリ
谷中 佑輔さん (大学院美術研究科 修士課程 彫刻専攻 平成26年修了)
後藤繁雄賞
藤井 マリ―さん (大学院美術研究科 修士課程 油画専攻 平成26年修了)
小山登美夫賞
佐々田 美波さん (美術学部 陶磁器専攻 平成26年卒業)
建畠晢賞
笹岡 由梨子さん (大学院美術研究科 修士課程 油画専攻 平成26年修了)
音楽関係
第8回セシリア国際音楽コンクール(旧 蓼科音楽祭 in 東京)
<弦楽器部門 大学以上専門の部>
第3位 尼崎 有実子(あまさき ゆみこ)さん (ヴァイオリン) 音楽学部 弦楽専攻 3回生
第4位 芦澤 春菜(あしざわ はるな)さん (コントラバス) 音楽学部 弦楽専攻 2回生
第26回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール
<弦楽器部門 大学生の部>
第5位 尼崎 有実子(あまさき ゆみこ)さん (ヴァイオリン) 音楽学部 弦楽専攻 3回生
第16回万里の長城杯国際コンクール
<アンサンブル部門> 第2位(1位なし)
久貝 ひかりさん (大学院音楽研究科 器楽専攻(ヴァイオリン) 3回生)
一樂 恒さん (音楽学部 弦楽専攻(チェロ) 平成26年卒業)
藤川 有樹さん (音楽学部 ピアノ専攻 4回生)
第34回来音会コンクール
奨励賞 来音会賞
川﨑 さやかさん (音楽学部 ピアノ専攻 2回生)
第8回東京芸術センター記念ピアノコンクール
入選
藤川 有樹さん (音楽学部 ピアノ専攻 4回生)
第5回アントニオ・サリエリ国際音楽コンクール
<ピアノ部門> 第3位(第1,2位なし)
田原 希美さん (音楽学部 ピアノ専攻 平成21年卒業)
第51回なにわ芸術祭音楽コンクール
<新進音楽家競演会 器楽の部> 新人奨励賞
櫟原 藍さん (大学院音楽研究科 器楽専攻(ピアノ) 平成22年修了)
第19回びわ湖国際フルートコンクール
入選・武者小路千家賞
大谷 加奈さん (音楽学部 管・打楽専攻(フルート) 平成22年卒業)
モーツァルト国際ピアノコンクール
第1位
中村 太紀さん (音楽学部 ピアノ専攻 平成24年卒業)
関連ページ
平成27年度公立大学法人京都市立芸術大学職員採用試験のお知らせ
平成27年度公立大学法人京都市立芸術大学職員(常勤)の採用試験を実施しますので,お知らせします。
募集概要
| 職種 | 受験資格 | 採用予定者数 | 採用予定日 |
| 事務 | 昭和55年4月2日以降に生まれた方 (学歴は問わないが,大学卒業程度の 学力を必要とする。) |
若干名 | 平成27年4月1日 |
試験内容
筆記試験
内容 : 教養試験(択一式)及び作文試験
試験日 : 平成26年7月6日(日曜日)
試験会場 : 京都パルスプラザ
第1次面接試験
内容 : 集団面接
試験日 : 平成26年8月上旬~中旬
第2次面接試験
内容 : 個別面接
試験日 : 平成26年8月中旬~下旬
最終面接試験
内容 : 個別面接
試験日 : 平成26年8月下旬~9月上旬
受験申込期間
平成26年5月21日(水曜日)から平成26年6月6日(金曜日)まで(消印有効)
受験案内・申込書の配布
平成26年5月21日(水曜日)から京都市立芸術大学,京都市役所,京都市各区役所・支所のまちづくり推進担当等で配布しています。本学ホームページからもダウンロードできます。
お問い合わせ先
公立大学法人京都市立芸術大学 事務局 総務広報課
電話 075-334-2200
横尾忠則客員教授による特別授業 「横尾忠則~自作を語る~(仮題)」 開催のお知らせ
この度,京都市立芸術大学では,絵画や小説などジャンルを超えて国内外で活躍されている,本学客員教授 横尾忠則氏による特別授業「横尾忠則~自作を語る~(仮題)」を開催します。
この特別授業は,一般の方もご参加いただけますので,興味のある方はぜひお越しください。
| 日時 | 平成26年5月27日(火曜日)午後2時から4時 |
|---|---|
| 場所 | 京都市立芸術大学 中央棟L1教室 |
| 住所 | 京都市西京区大枝沓掛町13-6 |
| 内容 | 公開鼎談形式による特別授業 聞き手 建畠 晢 京都市立芸術大学 学長 進 行 小山田 徹 同 教授 |
| 入場料 | 無料 |
| 申込み | 不要 |
| 問合せ先 | 京都市立芸術大学 教務学生課 美術教務担当 電話 075-334-2220 |
| アクセス | 交通・アクセスのページをご覧ください。 |
須川展也客員教授による公開レッスンを開催
5月15日(木曜日),本学交流室において,国内外で活躍され,サクソフォンを学ぶ多くの若者の目標的存在である須川展也客員教授による公開レッスンを開催しました。
このレッスンは,今年度新設されたサクソフォン実技を受講する管・打楽専攻1回生2人を対象に公開で行われ,同専攻の学生をはじめ多くの学生が聴講しました。
前半は学生一人ずつに,個人レッスンが行われ,須川客員教授からは,ビブラートをコントロールすることやメロディの基本ルール,息の使い方などの技術的な指導に加え,御自身の体験談を交えた「本番で緊張しない方法」についてもお話しされました。
後半は,学生2人に,須川客員教授,國末貞仁非常勤講師が加わり,カルテットのレッスンが行われました。須川客員教授からは,「『音程は友情』という言葉がある。1人が少し高い音を出したとき,それを正すのではなく,みんながその音に合わせる気持ちが大事。誰が何をやっているか,アンテナを張ってほしい。アンサンブルをする時は,一緒に演奏する人と会話をして作っていくと楽しい。」と学生にアドバイスされました。
レッスンを受講した学生
福田彩乃さん(管・打楽専攻1回生)
レッスン曲:ピエール・マックス・デュボワ サクソフォン協奏曲
「大御所と言われる先生のレッスンで,しかも,公開だったので,とても緊張しました。須川先生は実際に吹いて下さるのでとてもわかりやすかったです。私も先生のように吹けるようになりたいです。」
村山瑞季さん(管・打楽専攻1回生)
レッスン曲:ポール・クレストン ソナタ 作品19
「緊張して,ちゃんと吹けなかったので,先生に申し訳なく思いました。しかし,こういう緊張感のある場で,自分のできていないところが明らかになって良かったです。」
カルテットのレッスン曲
ジャン=バティスト・サンジュレー サクソフォン四重奏曲第1番作品53
須川展也客員教授プロフィール
サクソフォニスト
1984年 東京藝術大学を卒業。サクソフォンを故・大室勇一氏に師事
1989年~2010年 東京佼成ウインドオーケストラ・コンサートマスター
1989年~2008年 東京藝術大学非常勤講師
2007年~ ヤマハ吹奏楽団常任指揮者
2011年 東京藝術大学非常勤講師
2012年 東京藝術大学客員教授
2013年~ 東京藝術大学招聘教授
関連ページ
芸術資源研究センターのページを設置
平成26年4月に開設した京都市立芸術大学芸術資源研究センターのページ及びフェイスブックページを開設しました。
今後,同センターの活動や研究プロジェクト,研究会などのイベント情報をお知らせしますので,ぜひご覧ください。